各種介護サービスを受けるには、介護認定を受ける必要があります

そうですね、まずは介護認定の分類について見ていきましょう
要支援と要介護の違いって?介護認定には大きく2つの種類がある

日本の介護保険制度では、「要支援」と「要介護」という2つのランクがあります。これらの違いについて説明しますね。
要支援(ようしえん)
症状:
生活面での自立が困難ではないが、身体的、精神的な理由により、一部の日常生活動作や社会参加に支援が必要な状態です。
例えば、軽度の認知症、軽い移動の制限、軽度の精神的な問題などが該当します。
認定方法:
要支援認定は、地域包括支援センターや介護支援専門員による面談やアセスメントを通じて行われます。
日常生活動作の状況や、必要な支援の内容などが評価されます。
要介護(ようかいご)
症状:
日常生活動作のほとんど、またはすべてが自立できない状態です。身体的、精神的な理由により、他人の支援や介助が必要です。
重度の認知症、寝たきり、重度の身体障害などが該当します。
認定方法:
要介護認定は、要支援と同様に地域包括支援センターや介護支援専門員による面談やアセスメントを通じて行われます。
日常生活動作の状況や、必要な介護の内容、介護を必要とする日数などが評価されます。
要支援と要介護の認定は、個々の状況や必要な支援の程度に応じて行われます。介護保険サービスの利用やサポートの提供は、この認定に基づいて行われます。
.png)
要介護の方が要支援よりも症状が重く、よりサポートが必要なのですね。
目的は利用者の生活の質の向上!

要支援の段階や主な症状、受けられるサポートについて説明します。要支援1と要支援2の症状の違いと支援内容の違いを以下に示します。
要支援1の症状と支援内容
主な症状:
軽度の移動の制限や筋力の低下などが見られる場合。
主な症状:歩行に支障を来す、日常の身の回りの動作が難しい、重い物を持つことができないなど。基本的な日常動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。
支援内容:
身体的な支援や日常生活のサポートが主な焦点です。
在宅での訪問介護や訪問看護などのサービスが提供され、身体的な介護や日常生活動作の支援が行われます。
要支援2の症状と支援内容
主な症状:
軽度の認知症や物忘れが増えて日常生活に支障がある場合。
主な症状:日常の予定やタスクを管理できない、時間や場所に混乱を感じる、物の置き場所を忘れるなど。筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。
支援内容:
認知症に関連した支援や精神的な支援が重視されます。
デイサービスや認知症サポート施設での日中の活動やリハビリテーションプログラムが提供され、社会参加や認知機能の維持向上が目指されます。
要支援1と要支援2では、症状やニーズが異なるため、提供される支援内容も異なります。要支援1では身体的な支援が中心ですが、要支援2では認知症関連の支援や精神的なサポートが加わります。これにより、個々のニーズに応じた適切な支援が提供されることが目指されています。
要介護は4段階に分かれている
介護度の種類とそれぞれの症状
介護度1
主な症状:
軽度の認知症状 身体的な自立支援が必要な軽度の状態。日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少し見られる。
介護度2
主な症状:
中等度の認知症状、日常生活動作における介助が必要(例:トイレ介助、食事の準備)。要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。
介護度3
主な症状:重度の認知症状 ほぼ全ての日常生活動作での介助が必要。日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車椅子を使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。
介護度4
主な症状:
重度以上の身体的障害 高度な医療や介護が必要な状態。要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。思考力や理解力も著しい低下が見られる。
介護度5
主な症状:
日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。
受けられる介護サービス
1. 訪問介護: 介護職員が利用者宅を訪問し、身体介助や生活支援を行う。
2. 施設サービス: 介護老人保健施設や介護老人福祉施設などの施設で、入浴介助や食事の提供などを受ける。
3. 通所介護: デイサービスやデイケアなどの施設で、日中の生活支援やリハビリテーションを受ける。
4. 特定施設入居者生活介護: 特定施設に入居し、24時間の介護や看護を受ける。
5. 短期入所サービス: 短期間だけ施設に入所し、家族の介護者が休養する間に利用する。
6. 訪問看護: 看護師が利用者宅を訪問し、医療的なケアや健康管理を行う。
7.福祉用具の利用にかかるサービス:日常における動作支障に応じた介護用品を利用できる。

これらのサービスは、利用者の介護度やニーズに応じて適切な形で提供されます。
介護認定を受ける手順

では実際にどのような流れで介護認定を受けられるのか見ていきましょう
介護認定を受ける手順
申請:利用者またはその家族が、地域の介護支援専門員に介護認定の申請を行う。
管轄の行政サービスにお問合せください。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
訪問調査:専門員が利用者宅を訪問し、日常生活や健康状態などを評価する。
市区町村等の調査員が自宅や施設を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
審査判定:訪問調査から結果判定までの過程で行われる審査内容
調査結果及び主治医意見書の一部の項目は、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます(一次判定)。
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)
評価結果の通知:評価結果に基づいて、介護度や必要な支援内容が通知される。
市区町村は介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
認定は要支援1~2と要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談します。
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
介護サービスの利用:介護度に応じた介護サービスを利用するために、介護保険制度を利用することができる。
介護サービス計画に基づいたさまざまなサービスが利用できます。
定期的な再評価:利用者の状況が変化した場合は、再度介護認定の申請や再評価が必要となる。
定期的な見直しを行うことで、適切な介護サービスの利用をすることができます。

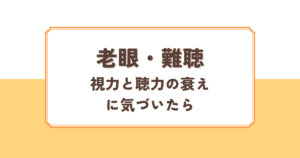

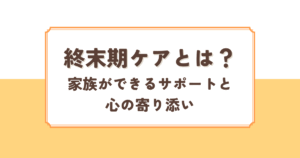


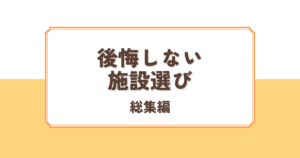
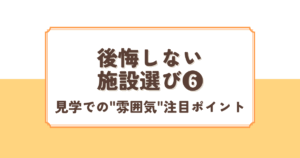
介護認定って、どんな種類があるんでしょうか?まだ、認定を受けたことがないのですが、どうすれば受けられますか?